「小学生の子どもがいても共働きできるのか」と考えたことありませんか?
小学生の子どもがいても、新たに働き始めたり、共働きを続けたりしている方はたくさんいます。
ただし、小学校ならではの不安や悩みも出てきます。
そこで、小学生の子育てをしながら共働きしている先輩ママが不安だったことや悩んだことを紹介します。
また、併せて先輩ママが共働きを続けていくために行った対策も教えます。
小学生の子育てをしながら共働きするのは、何か目標があるからではないですか?
子どもの教育資金を貯めたかったり、自分自身の社会的な役割が欲しかったりなど人それぞれ違った目的があるのではないかと思います。
そのような目的を実現させるために、ぜひこの記事を読んで小学生の子育てをしながら共働きしていく方法を知ってください。
目次
小学生の子育てをしながら共働きしても大丈夫?

小学生の子どもを子育てしながら共働きしても大丈夫です。
小学生になったら働こうと考えている方も働き始めて大丈夫です。
なぜなら、子どもも小学生になって成長しているので自分で出来ることも増えます。
実際に、共働きで小学生の子育てをしている方はたくさんいるので安心してください。
たとえば、小学校は送り迎えしなくても、登校班などのグループで集団登校するので見守りの必要がなくなります。
ただし、小学校ならではの問題にも直面する可能性はあるので、具体的にどのような問題が起こりそうなのか次の章で解説します。
小学生になったら子育てが楽になる訳ではない

子供が小学校に入ったら頑張って働こうと思っているママも多いのではないでしょうか?
いざ働こうと思っても、「小学校に入学したら、これまでとは違って大変なことがたくさんありそう」と不安も出てきますよね。
実際に、小学校に入ってからの苦労やぶつかる壁というものがあり、それらを以下の言い方をすることがあります。
- 小1の壁
- 小4の壁
それぞれ詳しく紹介します。
小1の壁とは?
子どもが小学校に入学すると、保育園時代と比べて子育てと仕事の両立が難しくなるのを「小1の壁」と言います。
たとえば、学童保育に入れなかったり、入れても保育園よりお迎え時間が早かったりと仕事を続けるのが難しいなどが挙げられます。
小4の壁とは?
学童保育では、低学年を優先して入所させてくれる所が多いので、小学4年生ごろから学童保育が利用できなくなるケースが多いようです。
また、9〜10歳という年齢は、精神的にも学力的にも悩みが出てくる時期なので親のサポートも重要です。
働きながら、子どものサポートをするのは大変で、小学校入学時とはまた違った悩みが出てくるため「小4の壁」と呼ばれます。
低学年の頃より、しっかりしてきたとはいえ1人でお留守番させるのは心配だと考える両親も多いのではないでしょうか。
フルタイムで仕事をしている場合、小学校が終わってからの時間は子どもが1人で留守番をしたり、友達の家に遊びに行ったりと様子を確認できないので不安に思う方もいるでしょう。
お友達など人間関係で悩む姿や、勉強が難しくなってきて苦労する姿を見れば、もっと親のサポートが必要だと感じるでしょう。
小学生になっても楽にならないのは壁があるから

先ほど、「小1の壁」と「小4の壁」について簡単に紹介しましたが、実際にそれらの理由で子育てが楽になっていない家庭が多くあります。
むしろ、仕事との両立が大変で、退職や時短勤務・パートに切り替えるママもいるのが実情です。
子どもが小学生になったら、働こうと考えていたママも、働き始めると預け先など問題が出てくるケースがあります。
ここが困るよ!小1の壁【10選】

小学校に入ると、何が大変なのかと思っているママに向けて、具体的に先輩ママが大変だと思ったポイントを紹介します。
具体的な内容なので、参考にしていただけると思います。
①学童の預かり時間が短い
保育園では、19:00ごろまで預かってくれる保育園が多く、フルタイムで働くママも時間の調整ができた方が多いのではないでしょうか。
しかし、学童保育では、18:00ごろまで預かり時間の所が多いので、1時間早くなると時間の調整が難しくなってきます。
さらに、下にもお子さんがいる家庭では、同じ時間帯に2か所にお迎えに行かなくてはならず大変さが増します。
②宿題のサポートが大変
小学校の宿題では、親が丸付けや音読を聞くなどのサポートが必要なところが多いです。
音読や計算カードを聞いて、やった内容を記載するなどしなければいけません。
帰宅してすぐに取り組んでくれる子どもだといいですが、大抵はうまくいかないでしょう。
宿題をやりたがらないわが子を説得しながら、食事の準備もしなければいけません。
学童保育に預けている場合でも、宿題をするかどうかは本人に任せるところも多く、必ず宿題は学童で済ませてくるという訳でもないようです。
保育園時代にはなかった宿題のサポートは、親も子どもも慣れるまでは大変です。
③時間がなく習い事に通わせてあげられない
小学校に入学すると、周りにも習い事をしている子どもが多くなってきます。
我が家も何か習い事をさせたいと思っても、平日は働いているとなかなか難しいですよね。
習い事の最大のハードルは、料金よりも送り迎えだと思っている方も多いのではないでしょうか。
まだ小さいうちは、1人で習い事に通わせるのも不安があるとなると、選択肢は土日に集中してしまいます。
土日に習い事の予定を入れれば、送り迎えは出来ますがママも休むときがなくって大変です。
④朝が早いので大変
保育園のときは、ママの出勤時間にもよりますが、9:00ごろまでに保育園に連れて行けばよいところが多いでしょう。
しかし、小学校になると家庭のライフスタイルは関係なく一律で集団登校するので、時間が早めです。
地域によって差はありますが、早いところだと7:00すぎには家を出なければいけないケースもあります。
集団登校に遅れないために、朝早く起きて準備をする必要があるので大変です。
⑤学校や地域活動に参加しなければいけない
小学生になると、PTA活動に参加しなければいけない地域も多いと思います。
役員になっていなくても、リサイクル活動など参加しなければいけない行事があるのも特徴です。
地域によっては、小学生になると自動的に子ども会に入会する仕組みになっており、子ども会の役員も回ってきます。
子ども会の役員は、PTA役員とも連携していてどちらの活動にも参加する必要があり大変です。
地域によって仕組みは違いますが、PTA活動や子ども会活動があり、親が参加しなければいけないところが多いです。
PTA活動は、平日昼間のことも多く有給休暇を使って参加しなければいけないケースもあるようです。
⑥平日行事が多く休まなくてはいけない
先ほど紹介したPTA活動のほかに、参観会や懇談会など小学校では平日に参加しなければいけない行事が多くあります。
防災訓練の一環として、引き渡し訓練をおこなう学校も多くあり、参加する必要があります。
平日開催の行事が多くなれば、有給休暇などを使って参加する機会も多くなるので、有給休暇が少なくなってしまうと心配なママも多いでしょう。
⑦長期休みの過ごし方が難しい
小学校に入ると、夏休みを始めとした長期休みがあるので、その過ごし方で悩まれる方も多くいます。
学童保育がある場合は、預け先が確保できて安心ですが、学校に行くのと違い給食がありません。
学童で用意してくれるところもあるようですが、お弁当持参のところが多いようです。
夏場のお弁当は、食中毒の危険性も高くなるので、毎日神経を使いながらお弁当を作るのは大変です。
また、長期休みでほかの子どもがお休みしていると、学童に行きたがらない子どももいるでしょう。
ママも、せっかくの夏休みなのに毎日学童に活かせるのも可哀そうと思う方もいるのではないでしょうか。
また普段は学童に預けずに、子どもが学校から帰ってくる時間までパートに行っているママなども、長期休み中は朝から子どもが家にいるので仕事にいけなくなってしまいます。
⑧学校の様子がわからないから不安
保育園と違い、学校にお迎えに行かないので、先生と顔を合わせる機会も少なくなります。
保育園では、お迎えに行ったときに子どもの様子を聞いたり、連絡帳を見たりして園での様子がわかります。
小学校に行くようになると、学校での様子は本人に聞くしかありません。
本人が学校での様子を話してくれる子であれば安心ですが、話してくれる子ばかりではありません。
私の周りのママ友でも、とくに男の子のママは学校での様子を聞いても「忘れた」しか言ってくれないから様子がわからないと言っていました。
とくに共働きで忙しくしているママは、毎日の家事や育児で精一杯であまり学校の話をしない子どもから様子を聞き出すのは大変です。
頻繁に先生に学校の様子を聞くわけにもいかないので、様子が分からず不安に思うママもいるでしょう。
⑨突然の持ち物の用意が大変
小学校では、突然持ち物を持っていかなくてはいけない時があります。
もちろん、事前にお知らせがあるので「突然」ではないのですが、お便りが親の元まで届いていないケースもあります。
よく探してみると、お便りがランドセルの下のほうに入っていたなどという事件も頻繁に起こります。
突然「明日、ラップの芯とペットボトルがいる」なんて言われたら、急に準備できなくて焦ってしまいまいませんか。
とくに共働きで、夜になって必要なものを言われてもお店も空いていないし困りますよね。
次の日に買って届けようと思っても、そのために仕事をお休みするのは難しいでしょう。
お便りなどの管理を子どもに任せていると把握できない場合があるので、親もしっかりとお便りの中身を確認する必要があります。
⑩子どもも新しい環境になれず不安定
子どもにとって、小学校入学は大きな環境の変化です。
保育園時代と違って、先生は個人個人にそこまで構ってくれませんし、勉強がはじまるのも大きな違いでしょう。
毎日、何時間も机に座って授業を聞くのは慣れない子どもにとっては大変な時間です。
小学校になって、ランドセルを背負って登校するのも、荷物も重いし大変ですよね。
宿題も毎日あると、慣れるまでは負担が大きいです。
そのような環境の変化で、子ども自身も不安があったり、疲れがあったりで不安定になってしまうときもあります。
共働きで働きながら子育てをしていると、不安定になった子どもをサポートしてあげたくても、時間がなくて十分なサポートが出来ずに悩むママもいるでしょう。
このような心配も?小4の壁【5選】

先輩ママが小学校に入って大変だと思った内容を紹介しましたが、高学年になるとまた違った大変さが出てきます。
小学校高学年になったらどのような悩みがあるのか、こちらも先輩ママの体験から紹介します。
①学童が終わり、放課後が心配
先ほどもお話ししたように、学童保育は低学年優先で入所するところが多いので、高学年になると預かってもらえないケースが出てきます。
学童保育が預かってくれる場合でも、本人がもう学童保育に行きたくないと言い出すケースもあります。
放課後に1人で留守番させたり、遊びに行かせたりするのは不安に思うママも多いでしょう。
この時期に、働き方を考え直す家庭もあります。
②長期休みの対応が必要
長期休みの対応も難しくなります。
学童保育に預けられない場合は、長期休みは1人で過ごすのでお昼ご飯の問題など考えるべき内容が多くあります。
また、子ども自身が自分のペースで宿題などを進められるかも心配な部分です。
③友人関係に悩む
10歳前後になってくると、お友達関係も複雑になってきます。
子ども自身もお友達関係で悩むケースも増えてきますし、トラブルが発生したときには相手の親と話し合いをするなどの必要が出てくる場合もあります。
④学習のつまずきが出てくる
高学年になってくると、次第に勉強の内容も難しくなってくるので、つまずきが出てくる子もいるでしょう。
勉強のつまずきを放置しておくわけにはいかないので、親のサポートが必要になってきます。
親のサポートだけでは難しい場合は、塾に通うなども検討しなくてはいけないでしょう。
⑤受験対策を始める
家庭によっては、中学受験を考えている方もいると思います。
中学受験を考えているなら、小学4年生頃から本格的に受験に向けた準備を始めなければいけません。
共働きで働きながら、中学受験のサポートをするのは、なかなか大変です。
小学校の壁を乗り越える7つの対策
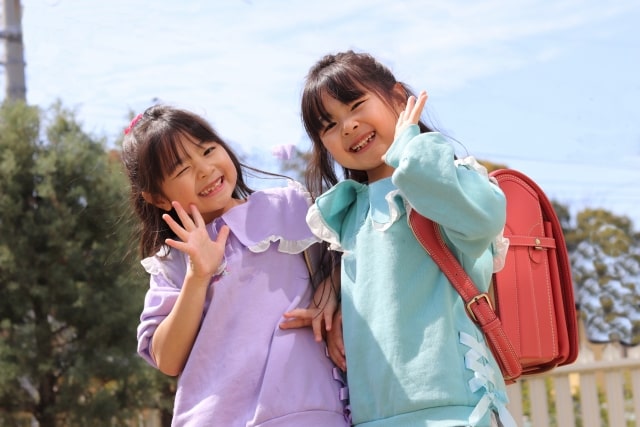
ここまで、小学校に入学してからの大変なポイントを紹介してきましたが、小学校の壁を乗り越えるために出来る対策を7つ紹介します。
少しでも、大変な思いをしなくて済むようにぜひ実践してください。
①夫婦の役割を決める
夫婦の役割はしっかり決めておいたほうがよいでしょう。
宿題のチェックはパパが担当するなど具体的に役割を決めておけば、子どもも覚えてくれます。
共働きなので、ママも少しでも楽にできるようにパパに協力してもらいましょう。
②連絡関係はママ友網を活用する
学校で必要なものや予定などは、すぐに聞けるママ友がいると心強いです。
明日の予定をかいた連絡帳を学校に忘れても、教えてもらえるママ友がいれば慌てなくて済みます。
小学校では、お弁当の日があったり、必要なものを準備する必要があったりするので、お互いに忘れないように声掛けできるママがいるといいですね。
③家事代行やファミリーサポートを利用する
学童保育は保育園よりもお迎え時間の早い場合が多いですが、どうしても残業など忙しい時はファミリーサポートを利用するのもよいでしょう。
あらかじめ登録が必要ですが、困ったときにお願いできるので登録しておくと心強いですね。
忙しくて、どうしても家事まで手が回らないときや体調不良のときなど、家事代行サービスを利用してみるのもオススメです。
無理だと思うときは無理せず頼れるものはいろいろ使って、乗り切りましょう。
突然の持ち物は事前準備しておく
学校でよく必要とされる持ち物には以下のようなものがあります。
- ラップの芯
- 新聞紙
- 卵パック
- ゼリーやプリンの容器
- 包装紙
- 段ボール
などです。
どれも、日常で使うものではありますが急に言われても翌日に用意するのが難しいものもあります。
そこで、普段から学校で必要になるかもと意識して、捨てずにとっておくといいでしょう。
少し収納スペースは使ってしまいますが、小学校の間だけなので慌てないためにも取っておきましょう。
また、とくに低学年のうちは鉛筆や消しゴムも頻繁になくします。
急いで買いに行かなくても済むように、鉛筆や消しゴムはあらかじめストックを準備しておくとよいでしょう。
習い事をさせる
習い事をさせたくても、送り迎えの時間が作れない方が多いかと思います。
しかし、習い事によっては送り迎えをしてくれる習い事があります。
代表的な例は、スイミングスクールでバスで送り迎えを実施しているところがあるからです。
学童保育に通っている子でも、学童までお迎えのバスが来てくれる習い事もあるので、習い事をさせるのであれば、お迎えがあるかどうか確認してみるとよいです。
送り迎えをしてくれる習い事に行かせると、放課後に何をしているか不安なママも心配しなくて済むようになります。
習い事をして、預かり時間を確保するというのもひとつの方法です。
居場所がわかるようにする
居場所がわかるようにしておくと、あまり心配せずに済むでしょう。
方法は、キッズケータイやGPS機能がついたキーホルダーを携帯させるなどの方法があります。
居場所の把握ができるので、お家にいるのか、お友達のお家に行っているのかなど確認できます。
また、災害なども想定して子どもに公衆電話の使い方を教えておくのもよいでしょう。
ママやパパの携帯番号を覚えてもらって、なにか連絡しなければいけないときは電話をするというのを練習させておくと安心できますね。
働き方を変えてみる
いろいろと対策を紹介しましたが、どうしても仕事との両立が難しい場合は働き方を変えてみるのも方法です。
フルタイムで働いているママは、時短勤務やパートなど働く時間を減らしてみると、収入は減ってしまいます。
しかし、子どもと過ごす時間は増えるので、子どもとの時間を優先したい場合は考えてみましょう。
まとめ:小学校ならではの悩みは対策して乗り切ろう

少しでも、小学生をもつ共働きの子育てママが楽になるように、いろいろとご紹介しました。
共働きの子育ては、未就学児も小学生も大変です。
成長しても、また別の大変さがあるのでなかなか落ち着きません。
働き方を変えるのは、少しハードルの高い内容ですがそれ以外の6つの対策は比較的取り組みやすい内容になっています。
できるとこから対策して、少しでも子どもと向き合える時間をぜひ確保してください。


